新型コロナウイルス後遺症の労災取扱いについて
新型コロナウイルスの罹患後症状(後遺症)の労災の取扱いに関する新たな通達が、5月12日付、厚生労働省より出されました。
職場で新型コロナウイルスに感染した場合、業務によって感染した(業務起因性と業務遂行性)と認められば労災保険の給付対象となり、従来から後遺症もその対象としていましたが、4月に罹患後症状に関する診療の手引きが取りまとめられたのを受け、後遺症の労災補償における取扱いが明確になりました。
通達の主な内容
具体的な取扱い
1)療養補償給付
医師により療養が必要と認められる以下の場合については、コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)として、療養補償給付の対象となる。
ア 診療の手引きに記載されている症状※に対する療養(感染後ある程度の期間の経過後に出現した症状も含む)
※疲労感・倦怠感や咳、息切れ、記憶障害、集中力低下、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害など
イ 上記アの症状以外でコロナウイルス感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養
ウ コロナウィルス感染症の合併症に対する療養
2)休業補償給付
罹患後症状(後遺症)により、休業の必要性が医師から認められる場合は、休業補償給付の対象となる。
なお、症状は数か月以上続く場合や、一旦症状が消失した後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や勤務時間等の調整が必要となる場合もあることに留意する。
3)障害補償給付
十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状が固定したと判断され後遺障害が残る場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。

相談等における対応
罹患後症状の労災保険給付に関する相談等があった場合には、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底すること。
周知
罹患後症状についても労災保険給付の対象となることについて周知すること。
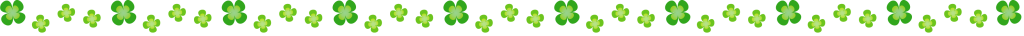
通達では、新型コロナウイルス後遺症の代表的な例である疲労感・倦怠感や咳、息切れ、記憶障害、集中力低下、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害など(手引きに記載のある症状)は労災保険の療養補償給付の対象になるとしています。
また、これらの症状のほか新型コロナにより新たに発症した、精神障害を含む傷病や合併症も労災の対象になるとしています。
療養補償給付がされると、労災指定病院等で自己負担なしで治療が受けられます。
療養補償給付を受けながら休業が必要な場合は、休業補償給付の対象となり、休業4日目から特別支給金と併せて賃金の80%が補償されます。
十分な治療をしても改善する見込みがなく、症状が固定したと判断される場合は障害補償給付に変わります。障害補償給付は障害の程度に応じて、年金と一時金で支払われます。

また、労働基準法では業務上の負傷・疾病で療養をしている間は、労働者を解雇してはならないと定めています。
新型コロナウイルス後遺症についても労災と認定されれば、当然に解雇制限が適用されます。
同手引きによると、「罹患後症状は数カ月続く場合もあるが、時間とともに軽快するケースが多い。職場復帰時には主治医の意見を参考に、労働時間の短縮や通院機会の確保など、職場での配慮が必要」としています。
新型コロナウイルスと労災
後遺症の取り扱いについては先述のとおりですが、ではそもそも新型コロナウィルスはどういう場合に労災認定をされるのでしょうか?
労災と認定されるためには、次の二つの要件が必要です。
〇業務遂行性
「業務遂行性」とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態において負傷などが発生したことを意味します。
例えば、事業場内で就業中に負傷した場合には、おおむね業務遂行性が認められます。休憩時間中で就業していない場合であっても、事業主の支配・管理下にあれば業務遂行性は認められます。また在宅勤務であっても同様です。
〇業務起因性
「業務起因性」とは、従事している業務と労働者の負傷などの間に相当因果関係(合理的な原因・結果の関係)があることを意味します。
事業主の支配下で業務に従事している場合(業務遂行性)には、原則として業務起因性があると考えられますが、すべてが認めれれるわけではなく個別に判断されます。

新型コロナウィルスと「業務遂行性」「業務起因性」
労災認定のために必要な「業務遂行性」と「業務起因性」。例えば”事業所内での就業中のケガ”などはこの二つが比較的わかり易いものですが、新型コロナウィルスではどのように判断されるのでしょうか?
厚生労働者が労災認定の具体的な事例を紹介しています。
1 医療従事者等の事例
【具体的な取扱い】
医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。
2 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例
【具体的な取扱い】
感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象となる。
(事例)
- 飲食店員Aさん
Aさんは飲食店内での接客業務に従事していたが、 店内でクラスターが発生し、これにより感染したと認められ支給決定された。
- 建設作業員Eさん
Eさんは勤務中、同僚と作業車に同乗していたところ、後日、同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、この同僚からの感染と認められて支給決定された。
3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例
【具体的な取扱い】
感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染した蓋然性(*)が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる。
*確実性が高い
①複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(事例)
- 営業職業従事者Cさん
感染経路は特定されなかったが、Cさんは発症前14 日間に、会社の事務室で営業業務に従事していた際、同じ事務室でCさんの他にも新型コロナウイルス に感染した者が勤務していたことが確認された。このため、Cさんは、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、かつ一般生活では感染するリスクは非常に低い状況と認められたことから、支給決定された。
②顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
(事例)
- 販売店員Aさん
感染経路は特定されなかったが、Aさんは発症前 14 日間に、日々数十人と接客し商品説明等を行うなど感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、かつ一般生活では感染のリスクが非常に低い状況と認められたことから、支給決定された。
- 保育士Eさん
感染経路は特定されなかったが、Eさんは、発症前 14 日間に、日々数十人の園児の保育や保護者と近距離で会話を行うなど感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、かつ一般生活では感染するリスクは非常に低い状況と認められたことから、支給決定された。
下記リンク先より抜粋
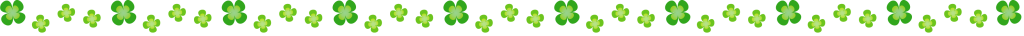

【まとめ】
今回の通達により、コロナウイルス感染後の長引く症状に対しても労災の対象となることが、はっきりと記載されました。令和4年4月の新型コロナウイルスによる労災請求件数は約8,098件、そのうち支給決定件数は2,132件と、令和4年度に入り請求件数は大きく増えています。今後、後遺症としての労災請求件数も増加すると思われます。
また通達には、労災保険についての相談には、後遺症は労災保険給付の対象とならないと誤解させるような対応をしないこと、後遺症も労災の対象となることを周知すること、の2点も書かれています。
企業の人事労務担当者は、コロナウィルス感染症とその後遺症も労災保険給付の対象であることをしっかりと理解し、従業員からの相談、申出には正しく対応するようにしなければなりません。
。
