障害者雇用の除外率制度の改正について
障害者雇用状況報告書とは
『障害者の雇用の促進等に関する法律』で義務づけられた報告です。
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークへ7月15日までに報告する必要があります。
近年の改正
令和4年12月に『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』の改正に伴い、令和6年4月から特に短い労働時間で働く一定の障害者を雇用率の算定に含めることができるようになりました。
また、令和5年3月に『障害者の雇用の促進等に関する法律施行令』が改正され、障害者の法定雇用率の引上げが段階的に施行されており、民間企業において令和8年7月には障害者法定雇用率は2.7%まで引き上げられます。

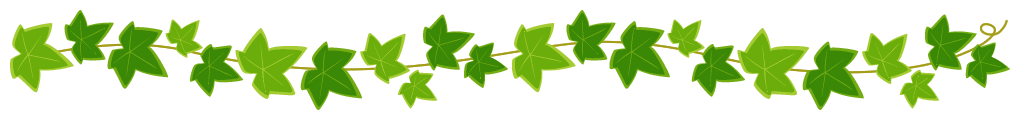
障害者雇用率制度
障害者雇用率制度とは、従業員が一定数以上の規模の事業主に障害者を雇用することを義務付けている制度で、その雇用人数の算出基準となっているのが障害者法定雇用率です。現在の民間企業の障害者法定雇用率は2.5%でありますが、令和8年7月からは2.7%まで引き上げられます。
| 令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業の障害者法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40人以上 | 37.5人以上 |
障害者雇用の除外率制度
上記の障害者雇用率制度に則り、障害者の雇用を義務付けられている一方で、職務の性質上、障害者雇用率を適用することに馴染まない業種も存在します。
具体的には、建設業・医療業・道路貨物運送業等が挙げられ、これらの業種については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除することにより、障害者の雇用義務が軽減されます。この除外率は、令和7年4月1日から設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられ、以下のとおり設定されています。
| 除外率設定業種 | 除外率 |
|---|---|
| ・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
| ・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
| ・港湾運送業 ・警備業 | 15% |
| ・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | 20% |
| ・林業(狩猟業を除く) | 25% |
| ・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 30% |
| ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
| ・石炭・亜炭鉱業 | 40% |
| ・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% |
| ・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 50% |
| ・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |

障害者の算定方法
(1) 障害者の雇用義務数を算出するに当たり、1,000人の常用労働者がいる場合、以下の計算式で算することができます。
1,000人×2.5%(令和7年5月時点障害者法定雇用率)=25人
この計算式から上記の除外率が適用される業種である場合は、業種 に応じた除外率を踏まえ、具体的な人数を算出します。例えば、業種が建設業である場合、除外率は10%ですので、
(1,000人-1,000人×10%)×2.5%=22.5人
1人未満の端数は切り捨てられ、雇用義務数は22人となります。
(2) これらに加え、雇用する障害者の障害の程度によっても一律に扱うことは難しいため、以下のとおり算定方法が別に定められています。たとえば、1人の週所定労働時間が30時間以上の重度身体障害者を雇用する場合には2人とカウントします。
| 障害の種類/週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 | 10時間以上 20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | ― |
| 身体障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 ※イ |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | ― |
| 知的障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 ※イ |
| 精神障害者 | 1 | 1 ※ア | 0.5 ※イ |
※近年の改正
ア:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定されます。
イ:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、0.5カウントとして算定されます。
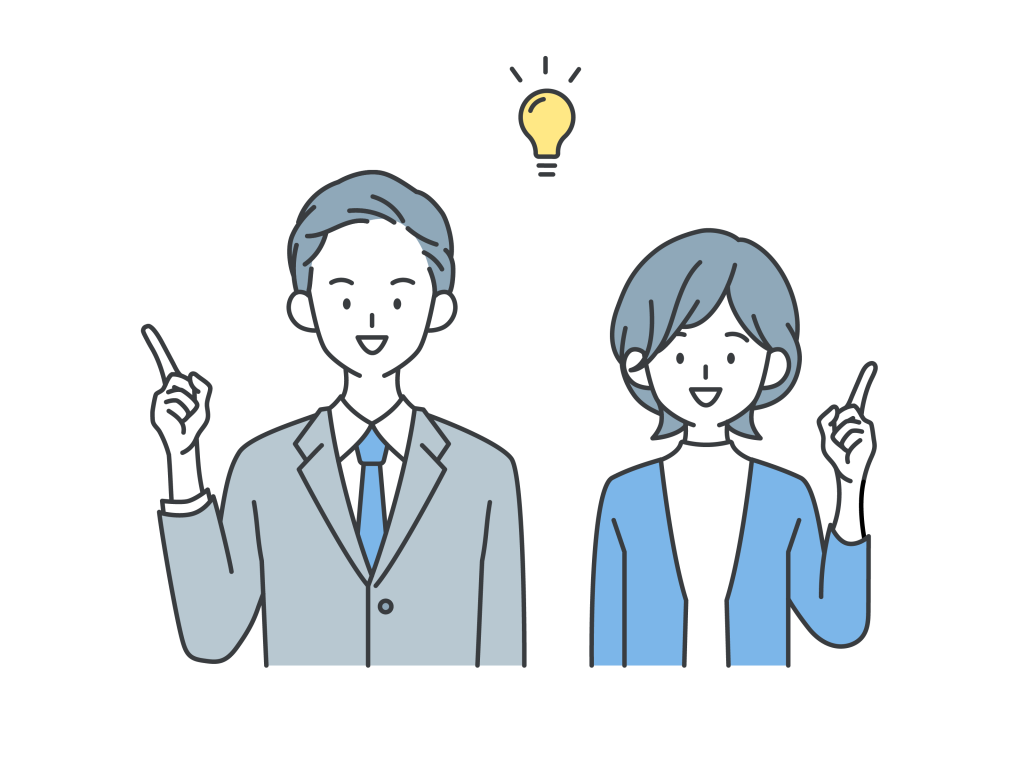
障害者雇用納付金・障害者雇用調整金・報奨金
常用労働者が100人を超える事業主は、障害者法定雇用率が達成されなかった場合、不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。例えば、常用労働者が1,000人の企業の場合、25人(1,000人×2.5%)の障害者雇用が必要でありますが、障害者雇用者数が20人であった場合、不足する障害者数は5人(25人-20人)なります。そのため、月額5万円×5人=月額25万円の納付金を納める必要があります。
反対に、常用労働者が100人を超える事業主で、障害者法定雇用率を超えて雇用している場合に、その超えた障害者の人数に応じて1人当たり月額29,000円の障害者雇用調整金が支給されます。ただし、障害者法定雇用率を超えて雇用している人数が年間120人を超える場合は、超過人数への支給額が、1人当たり月額23,000円となります。
また、常用労働者が100人以下の事業主には、各月の常時雇用している障害者の年度合計数が一定数(※)を超えて雇用している場合に、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額21,000円の報奨金が支給されます。
ただし、支給対象人数が年間420人を超える場合には、超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円となります。
(※)各月ごとの算定基礎日における常用障害者数の年度間合計数が、「各月毎の常用雇用労働者数に4%を乗じて得た数の年度間合計数」又は「72人」のいずれか多い数

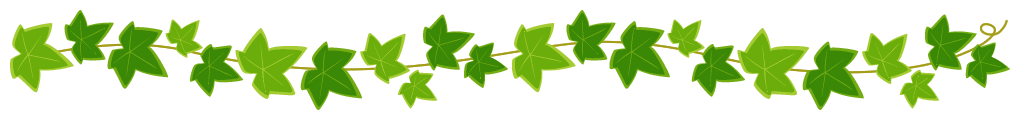
毎年、6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況をまとめている「障害者雇用状況(令和6年)」によると、民間企業(常用労働者数が40人以上の企業)に雇用されている障害者数は67 万 7,461.5人でした。前年と比べると3万5,283.5人増加しており、この結果は、雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新しています。
既に令和8年7月には民間企業の障害者法定雇用率は2.7%まで引き上げられることが決定しており、障害者の採用競争もより一層激化することが予想されます。企業においては、採用活動に力を注ぐだけでなく、障害者の能力向上のための教育訓練の実施、障害者の援助ができる体制整備等、様々な対策に取り組むことが大切です。
取組みの一例といたしまして、障害者雇用の促進及び雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下である事業主に限る。)を厚生労働大臣が認定する「もにす認定制度」があります。この認定を受けた事業主の情報は、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます。また、ハローワークの求人票に認定マークが表示され、積極的に周知広報が行われる等のメリットがありますので、このような制度の活用も検討してみてはいかがでしょうか。
