育児短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための措置が講じられています。これらは令和7年4月1日から段階的に施行されます。
今回の改正で、育児短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加されました。

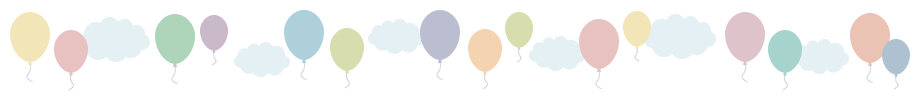
〇改正の概要
会社が、育児短時間勤務制度を利用させない労働者を定めている一定の場合に、代替措置を講じることが義務付けられていますが、今回の改正で代替措置の選択肢に「テレワーク」が追加されました。
〇育児短時間勤務制度
そもそも育児短時間勤務制度とは、
「会社は、3歳未満の子を育てながら働いている労働者に対して、本人が希望した時に所定労働時間を短くして、子を育てながら働くことを容易にする措置を講じなければならない」
という内容として、育児・介護休業法で定められているものです。(第23条第1項)
また、この制度は
“1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの”
としなければなりません。
「原則として6時間とする措置」
通常の所定労働時間が1日7時間45分である事業所を勘案し、短縮後の所定労働時間が1日5時間45分から6時間までであれば、許容されています。
「6時間とする措置を含むもの」
短時間勤務を希望する労働者の選択肢に、“所定労働時間を1日6時間とする措置”が含まれているようにする必要があります。
例)通常の所定労働時間1日8時間の労働者が、制度利用を希望した場合の選択肢(短縮後の所定労働時間)
- 1日5時間
- 1日6時間
- 1日7時間
この他にも、所定労働日数を短縮する措置等をあわせて設けることも可能で、労働者の選択肢を増やす措置がより望ましいと考えられます。

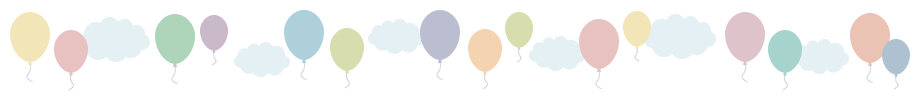
〇育児短時間勤務制度の対象外
会社は、以下のいずれかに該当する労働者からの育児短時間勤務の申出は拒むことができます。
- 日雇労働者
- 1日の所定労働時間が6時間以下の労働者
- 労使協定締結で対象外とした場合、以下の労働者
- 入社1年未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
- 業務の性質・実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
上記③を対象外として労使協定を締結する場合、対象外となる業務の範囲を具体的に定めることが必要です。
行政の告示では以下のような業務が例示されています。(平成21年厚生労働省告示第509号)
- 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務
- 労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
- 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
- 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
- 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務
これらはあくまでも例示であり、これら以外の業務は該当しないというものではなく、また、これらであれば認められる業務に該当するというものでもない旨をご留意ください。

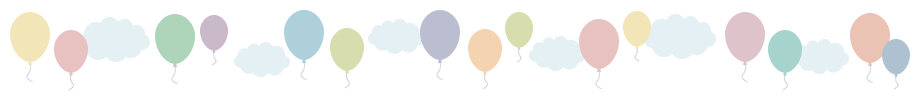
〇育児短時間勤務制度の代替措置
さて、このように「業務の性質・実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定を締結し、短時間勤務制度の対象外とした労働者に関して、会社は代替措置を講じなければなりません。
代替措置として認められるものは下記の通りです。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ (時差出勤)
- 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
ここに、今回の法改正で加わったのが「⑤テレワーク」です。
令和7年4月1日以降は、上記①~④に加えて「⑤テレワーク」も選択肢として追加されていますので、①~⑤のうち、いずれかの措置を講じればよいということになります。
また、いずれかの措置を決定した場合には、就業規則の見直しと労働者への周知が必要です。

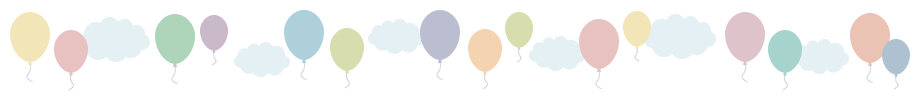

今回お伝えした改正内容の他にも、
「3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じること」
が、令和7年4月1日以降、新たに会社に“努力義務”として課されます。
これらの改正を機に、社内の業務内容を見直し、新たな働き方としてテレワーク導入を検討してみてはいかがでしょうか。
