令和7年(2025年)の年末調整の変更点
税制改正に伴い、令和7年年末調整は、去年までと大きく異なってきます。
大きな改正点は2つです。
① 所得税の基礎控除額及び給与所得控除額の見直し
② 特定親族特別控除の創設
これに伴い、扶養控除申告書などの書面様式も更新されているため、紙申告で年末調整を行う事業所は最新の様式を国税庁HPなどからDLするよう気を付けましょう。
では実際には何がどう変わったのか、次項より変更点を確認していきますが、先にそもそも所得税に関わる基本事項を極簡潔にまとめます。

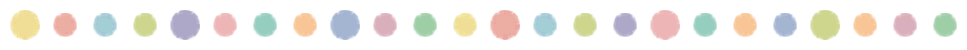
◆「控除」「所得」「課税」の基本
・所得税は「収入」から「必要な経費や控除」を差し引いた額にかかります。
・「控除」は税金を引く前の所得を少なくする仕組みで、「基礎控除」「給与所得控除」などの種類があります。
・「基礎控除」はほとんど全ての人に使える最低限の控除です。
・「給与所得控除」は、給与収入者(社員・パートなど)が経費相当分を差し引くための控除です。
⇒基礎控除/給与所得控除ともに、極々簡単に言い換えると「額面の収入金額を得るためにかかった必要経費」なので、その金額分は所得税がかからない様にしましょう、ということです。
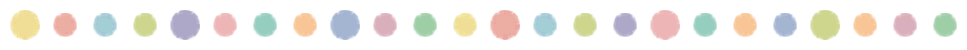
1. 所得税の控除額の見直し
基礎控除:合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
この改正に伴い、令和8年分以降の源泉徴収税額表も改正されます 。
⇒いわゆる必要最低限の収入にかかる経費枠です。
従前は「103万円の壁」のうち48万円は基礎控除と相殺されるため、残りの55万円が給与所得控除で相殺され、額面収入が103万円以内であれば、個人に所得税がかからないいわゆる扶養内での収入となっていましたが、基礎控除額の引き上げ+租税特別措置法に基づく特別加算額が追加された今年の改正で、年収の壁の上限が引きあがり、所得税のみに限ってみれば最低年収が「160万円」まで拡張されています。
基礎控除が引き上げられたため、扶養親族の要件も見直しが入っています。
従前の税法上の被扶養者は年収103万円以下の方でしたが、新たに123万円以下と上限が引き上げられています。勤労学生については、年収150万円まで上限が拡大されています。いずれも所得にして10万円分上限が拡大されたものとなります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 改正前 |
基礎控除額 2025~ |
|---|---|---|
| ~132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 336万円以下 | 88万円(58万+30万) | |
| 489万円以下 | 68万円(58万+10万) | |
| 655万円以下 | 63万円(58万+5万) | |
| 2350万円以下 | 58万円 | |
| 2350万1円~ | 改正なし | |

給与所得控除:給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。
これにより、令和7年分以降の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
⇒いわゆるサラリーマンや事業会社に勤める人であれば、基本的にはその会社から支給される給与が収入となるため、その収入金額に応じて必要経費分として収入から控除された金額に所得税が課税されます。
| 給与収入額 | 給与所得控除 改正前 |
給与所得控除 2025~ |
|---|---|---|
| ~162万5000円以下 | 55万 | 65万 |
| ~180万円以下 | 収入額*40%-10万 | |
| ~190万円以下 | 収入額*30%+8万 | |
| 190万1円~ | 改正なし | |

2. 特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除: 所得者が特定の親族を扶養している場合、その親族の合計所得金額に応じて控除できる「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族とは年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を指します。
扶養親族等の所得要件: 基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件も改正されました。
⇒従前の特定扶養親族としての扶養控除も併存しています。今回の新控除は、配偶者特別控除と同じで、額面収入が188万円以下の場合、特定親族の収入に応じて両親など扶養している納税者が控除を受けることが出来るようになります。
最大で63万円、最低でも3万円の特定親族特別控除が適用されるため、19~22歳までのご家族がいる場合、間違いなく収入を申告する様留意が必要です。
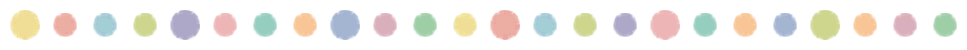
◆その他の改正ポイント
源泉徴収簿の記載
特定親族特別控除の適用がある場合、国税庁ホームページに掲載されている「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」は計算に対応していないため、余白部分に控除額を追記するなどして計算を行う必要があります。
給与所得の源泉徴収票
特定親族特別控除が創設されたことにより、「給与所得の源泉徴収票」も改正されました。控除の適用がある場合は、源泉徴収票に控除額等を記載してください。
⇒いずれも国税庁HPなどから様式をDLする場合、対応が必要になるため注意しましょう。
昨今多くの事業所にて、各企業がリリースしている人事労務ソフト/システムを利用していると考えられますので、各ソフトにて今般改正にも対応がなされると考えられます。
そのため、逐一各システムの更新情報やパブリッシャーの公式アナウンスは確認するように努めましょう。

住宅借入金等特別控除
調書方式の導入:令和7年分から、「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用が一部で可能になります。
添付書類の変更:調書方式を利用する人は、「住宅借入金等の年末残高証明書」の添付が不要となります。
⇒マイナポータルを用いた簡略化の一環で、ペーパーレス推進のための仕組みです。
金融機関を通して所定の申請を行っている人が対象になり、いわゆる残高証明の添付を省略できます。対象にならない人に関しては、従前と同じように残高照明の添付がなければ住宅ローン控除が適用されませんので、気になる人は住宅ローンを組んでいる金融機関へ早めに確認することを強く推奨します。
また、マイナンバー/マイナポータルの設定が必要になりますが、各個人で設定しなければなりませんので、そちらの対応も必要になる点にご留意ください。
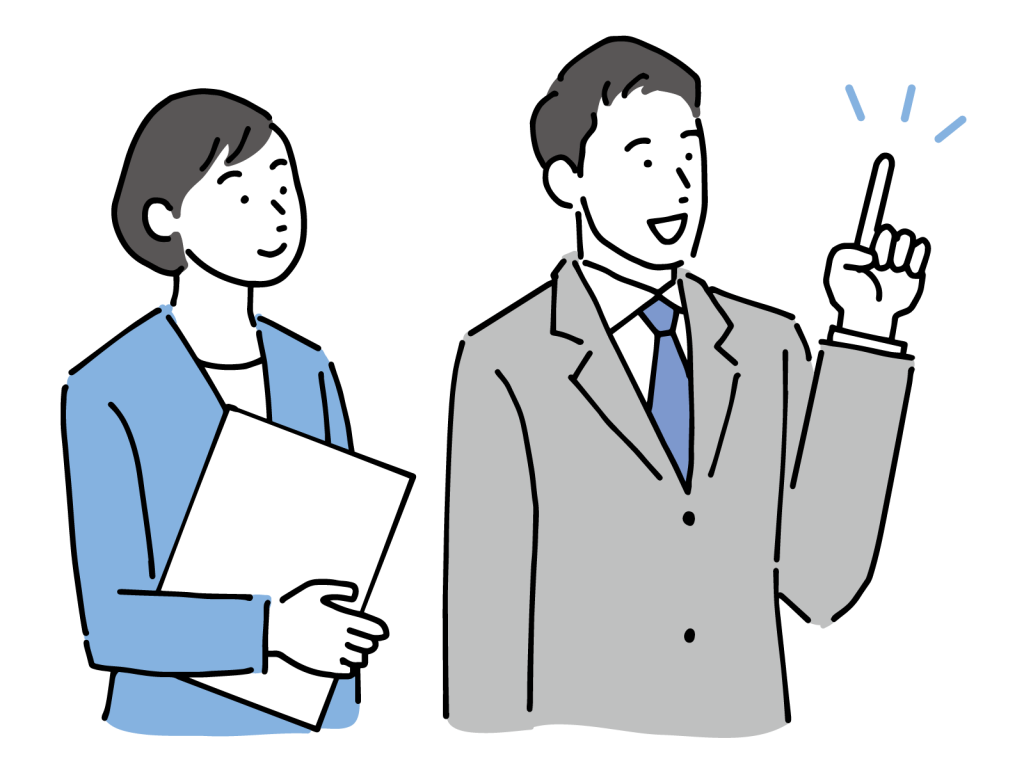
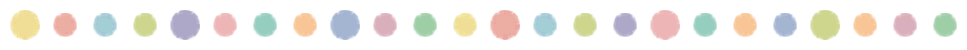
◆終わりに

実務上では、やはり控除額が変更になる点や、昨年までは収入上限を超過してしまった学生などの扶養親族が新たに各控除対象親族となる可能性が高いため、より正確な所得者本人および扶養親族からの申告が求められます。
また、毎年多くの問い合わせがありますが「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」とは全く意味がことなるものです。
特に社会保険上の被扶養者となっている配偶者は、健康保険の扶養認定について、130万円未満という用件は未だ何らの変更がないため、所得税がかからなくなったからといって長時間働くようになると、今度は社会保険に加入しなければならない、といった事例が発生することも考えられます。(19~23歳未満の健康保険上の被扶養者については、‘25/10/1から150万円未満の収入であれば、被扶養者認定されるように厚生労働省からも通知がでています。)
大きな改正がある時は、実務担当者にしてみれば頭が痛いことばかりですが、これを機に社内処理をIT化する、業務フローを見直して無駄をなくすなど、できる限りの準備をして乗り切っていきましょう。
(出典、参考)
国税庁 令和7年分年末調整のしかた
住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について
【保発0704第2号】厚生労働省保険局長通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」
