会社が対応しなければならないセクハラについて
近年、何かと話題になることが多いハラスメントですが、そもそもの定義や、会社が何かしなければいけない法的根拠などはあるのでしょうか?
今回は大手マスコミや国の省庁においても事案が発覚し、昨今では裁判になることも珍しくない、会社が対応しなければならないセクハラに関して掘り下げてみたいと思います。
※本稿においては一部法律などの名称を、便宜上一般的に取り扱われる名称にて表記、または省略して記載しています。


● 基本情報と定義
まずはセクシュアルハラスメントについてそもそもの定義や、基本的な情報についてまとめていきます
なお、「ハラスメント(harassment)」とは、英語本来の意味合いとしては、「悩ます、嫌がらせ」といったものです。
職場におけるハラスメントは「上司や同僚の言動が本人の意図とは関係なく、相手を不快にさせたり、傷つけたり、不利益を与えたりすることで、就業環境を害する行為」が該当するものと考えられています。
| 名称 | 定義 | 関連法律 |
|---|---|---|
| セクシュアルハラスメント | 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること。 | ・男女雇用機会均等法第11条関係 (労働施策総合推進法第30条関係) |
続いて、各語句の定義です
「職場」とは
労働者が通常働いているところはもちろんのこと、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。
「労働者」とは
正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者です。
また、派遣労働者については、派遣先事業主/派遣元事業主であるかを問わず、自ら雇用する労働者と同様に取り扱う必要があります。

「性的な言動」とは
性的な内容の発言や性的な行動のことをいいます。
例):性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(うわさ)を流すこと、性的な冗談やからかい、私的な食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと、性的な関係を強要すること、不必要な身体接触、わいせつ図画を配布/掲示すること、強制わいせつ行為など
セクシュアルハラスメントの「行為者」と「被害者」
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒なども行為者になり得ます。男性も女性も行為者にも被害者にもなり得ます。
また、異性に対するものだけでなく、同性に対する性的な言動もセクハラになり得ます。
被害者の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか)や性自認(性別に関する自己認識)に関わらず、性的な言動はセクハラに該当する可能性があります。
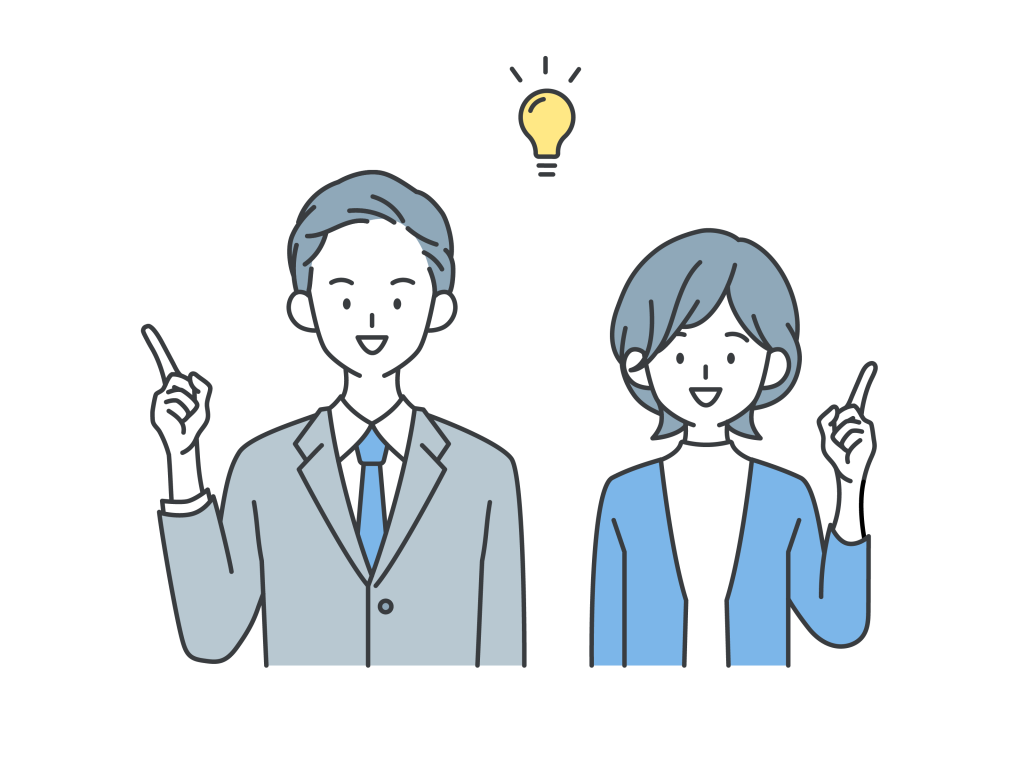
続いて、セクハラの典型的パターンとして類型される2種類を見ていきます
対価型セクハラ
性的な言動に対する反応を理由として、解雇/降格/減給などの不利な取扱いを行うもの。
例):上司が食事や交際を断られたことを理由に部下の評価を下げる、不当な扱いをする、理不尽に叱責する、等
環境型セクハラ
性的な言動により、就業環境が不快・不安となり、労働者の職務遂行に悪影響を与えるもの。
例):職場で性的な噂話や卑猥なポスターを貼る、事務所内で上司が腰や胸などを度々触るので、また触られるかもしれないと思うと仕事が手に付かず就業意欲が低下している、同僚が取引先でプライベートな性的内容の情報を意図的に流布したためそのことが苦痛に感じられて仕事が手につかない、等。
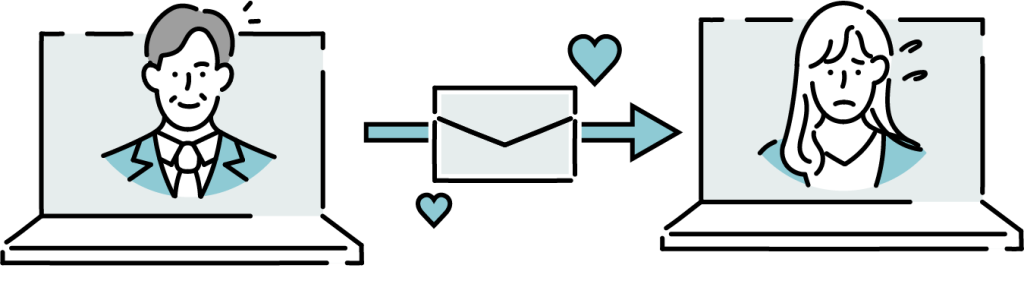
最後に会社が講ずべき防止措置(事業の規模を問わず、事業主の義務として規定)
- 方針の明確化と周知啓発
⇒就業規則への明記や社内研修の実施により、職場でのハラスメントがあってはならないことを明確にすると共に、行為者については厳正に対処することを規定し、全ての関係者に対して周知/啓発する。 - 相談・苦情処理体制の整備
⇒相談窓口の設置、相談者への配慮など、迅速かつ丁寧な対応ができるようにする。 - 事後の迅速かつ適切な対応
⇒早急かつ正確な事実確認のもと、加害者への適正な措置/被害者への速やかな配慮措置、再発防止措置などを逐次実行する。 - プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
⇒被害者はもちろん加害者や、相談者のプライバシーを保護するため必要な措置を講じる。併せて、相談したこと、被害を訴えたこと、事実関係の確認に協力したこと等に対する、報復や不利益取り扱い等の防止措置を定め、全ての関係者に周知/啓発すること。
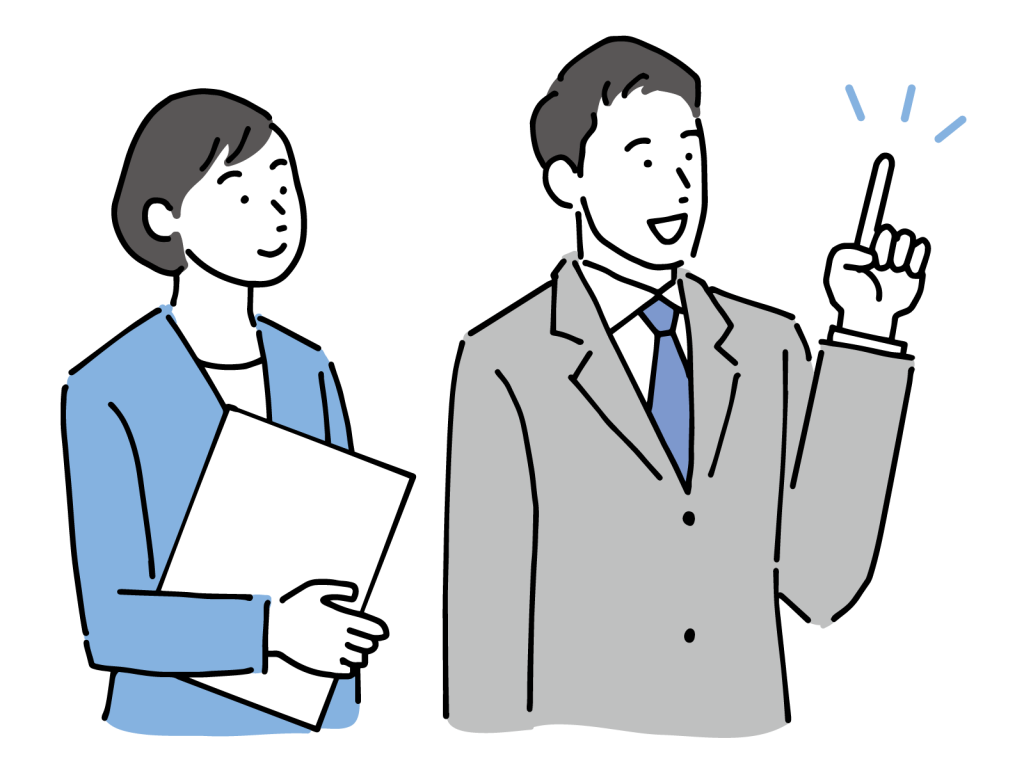

● 会社がとるべき措置や対応策について
会社としては、やはり就業規則及び規則に準ずる規定の整備が最優先といえるでしょう。また、就業規則自体の効力にも影響することですが、会社が示した各ハラスメント対策/防止指針を、明確に従業員に周知/啓発していくことが求められます。
併せて、研修や講習などを実施することで、ハラスメントそのものへの知識と理解を深め、決してあってはならないことである、との共通認識を全社的に共有することも有効だと考えられます。
また、旧態依然とした思想や職場の慣例が引き続いている環境の場合、いわゆる性別役割分担意識が根強く残っており、その認識に基づいた言動/行動が各ハラスメントと受け取られることは大いに考えられます。
昨今の社会情勢においては、もはや知らなかったでは済まされない、重大な事案として認識されているのがハラスメントであります。一従業員の個人的な問題、または当事者間の痴情のもつれとして切り捨ててよいのか、判断に困る難しい事案もあるかもしれません。
会社内で対応に困る場合は、弊所の様な社外の労務に関する専門家や、所轄の労働局または労働基準監督署といった、客観的に判断できる機関へのご相談も検討いただければと思います。


今回は会社におけるセクハラについてでした。
女性の社会進出が当たり前の世の中になると共に、従来は男性の比率が高くなかった保育士や看護師の様な職業も近年その割合が高まってきているという報告もあります。※1,2
※1 総務省国勢調査の推計によると平成12年の保育士就業者数は,36万1,488人,うち男性は4,666人で,全体に占める割合は1.3%でしたが,平成22年では,就業者数は47万4,900人,うち男性は1万3,160人で,割合も2.8%に上昇しています。
※2 令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、平成24年の就業看護師1015744人の内、男性は63321人(6.2%)だったのが、令和4年には就業看護師1311687人の内、112164人(8.6%)まで上昇しています。
その一方で、「昔の当たりまえ」をアップデートしていくには、まだまだ時間が必要なのだろうと感じています。
「男女同権とは、男の地位が女の地位まで上がったことなのです。」
太宰治はこう記していましたが、果たして令和の時代は太宰が言ったことが正しいのでしょうか、あるいは本来の意味での男女同権が進められていくのでしょうか。

※参考/出典
厚生労働省:あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
厚生労働省:職場におけるハラスメント対策パンフレット
厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室:平成 27 年 6 月作成 パンフレット№ 11
事業主の皆さん職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義 務 です!!
内閣府男女共同参画局 :男女共同参画白書平成26年版
厚生労働省:令和4年衛生暁斎報告例(就業医療関係者)の概況
男女雇用機会均等法
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第17条(第1項 略)
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
