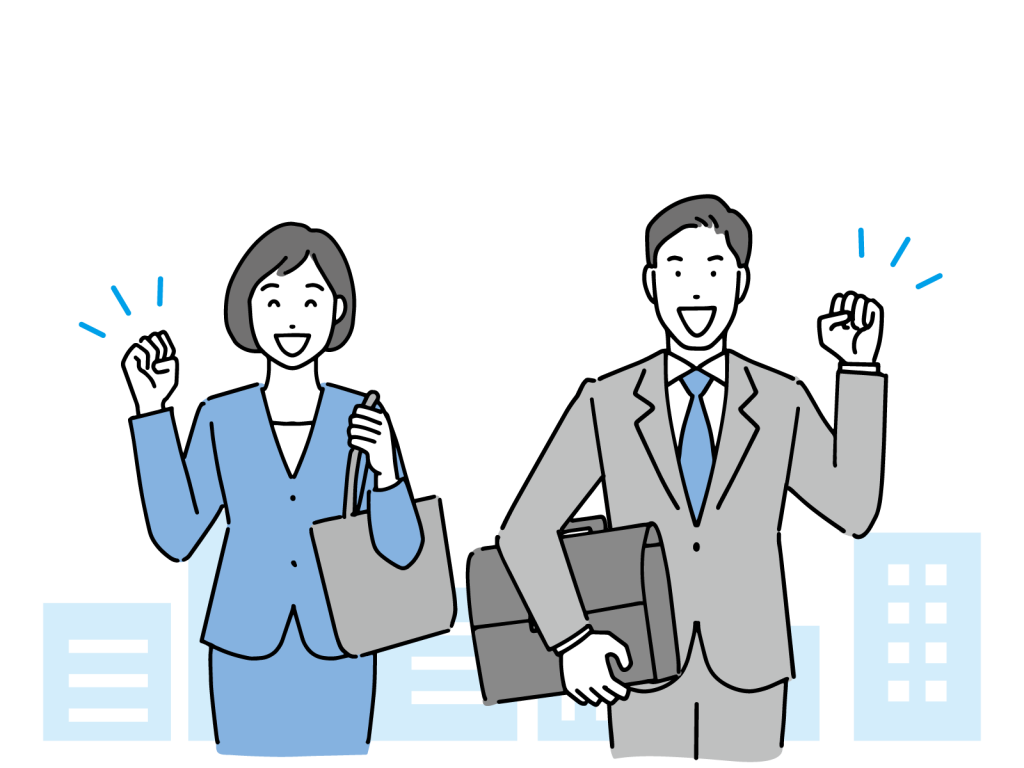カスタマーハラスメント対策について
2025年6月11日に『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律』が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントの防止措置が会社の義務となります。施行日は、公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日です。

社会問題化しているカスタマーハラスメントですが、厚生労働省の調査によると、過去3年間で見た時に10人に1人の労働者が受けたことがあると回答しました。また、カスタマーハラスメントに対して予防・解決の取り組みを実施している会社の割合は約65%にとどまり、3社に1社は特に何の取り組みも実施していないことになります。(令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査)
冒頭にお伝えした通り、近いうちに会社としての措置が義務付けられ、今後ますますカスタマーハラスメント対策が求められるでしょう。
また、カスタマーハラスメントを放置してしまうと、従業員に過度なストレスを与えメンタルヘルスの不調を発生させたり、会社としての安全配慮義務違反として責任を問われたりする可能性があります。
ですので、今回はカスタマーハラスメントとは具体的にどういった行為なのか、また、会社が取り組むべき対策にはどのようなものがあるのかについて解説していきます。
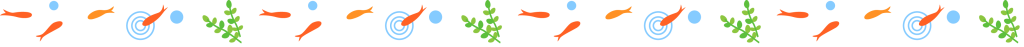
〇カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
2022年に厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公開しており、この中でカスタマーハラスメントについて定義しています。
以下はこのマニュアルの内容に沿って記載していきます。
定義
カスタマーハラスメントとは
① 顧客等からのクレーム・言動のうち、
② 当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、
③ 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、
④ 当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
まず、カスタマーハラスメントとは顧客からのすべてのクレームを指すわけではないことに注意が必要です。
クレームとは要求や主張のことですが、顧客からの正当なクレームに対しては、会社として真摯に対応する必要があります。
ただし、そもそもクレームの内容が著しく妥当でない場合や、その実現のための手段・態様が度を過ぎている場合にカスタマーハラスメントに該当する可能性があります。
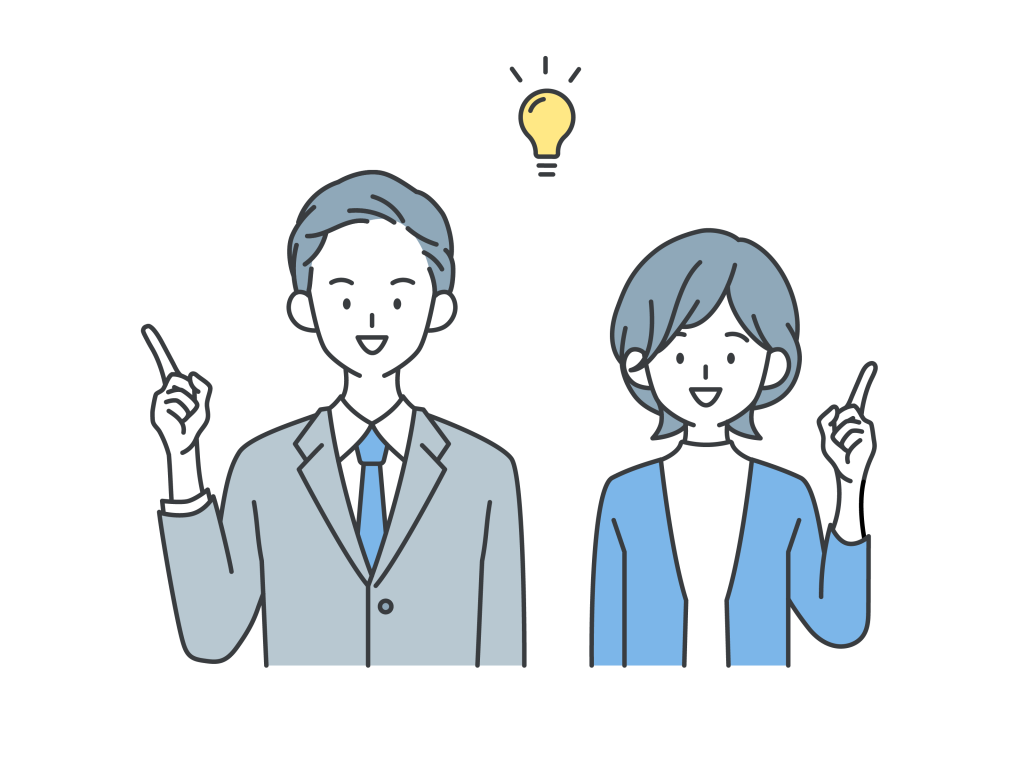
定義②の『顧客等の要求(クレーム)の内容が妥当性』ですが、妥当でない場合の例は以下のようなものが挙げられます。
- 会社の提供する商品・サービスに、瑕疵(何らかの欠陥、傷など問題があること)や、過失(注意義務を怠ったために損害を発生させること)が認められない場合
- 要求の内容が、会社の提供する商品・サービスの内容とは関係が無い場合
また、定義③の『要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの』の例は以下のようなものが挙げられます。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 土下座の要求
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 従業員個人への攻撃、要求
このような行為によって労働者の就業環境が害されるものをカスハラと定義しています。
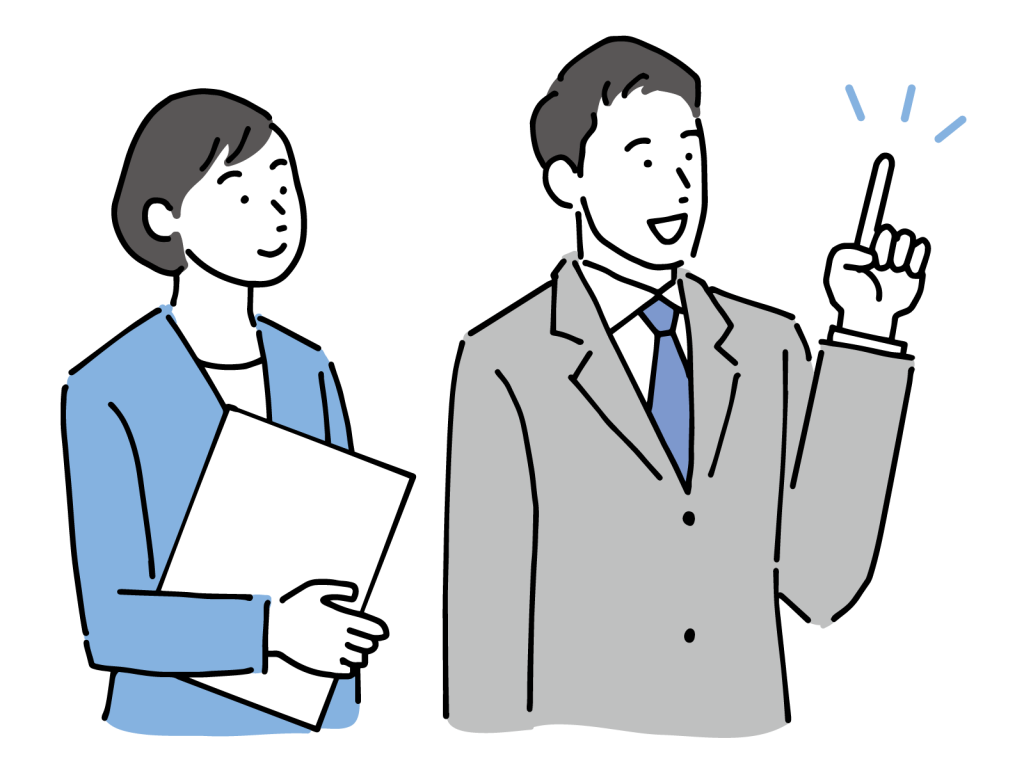
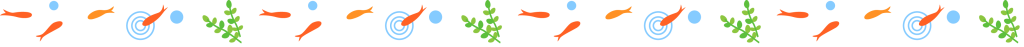
〇会社に求められる対応
法改正によって会社に義務付けられる措置の内容は、今後指針で示される予定です。
現在決まっている内容は以下の通りです。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備・周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
すでに義務付けられているセクハラ・パワハラ等に準じたような内容となっています。
〇具体的なアクション
カスタマーハラスメントの判断基準は業種や企業文化等の違いから、会社ごとに異なる可能性があります。そのため、自社におけるカスタマーハラスメントの判断基準を明確にした上で、考え方や対応の方針を会社全体で周知・共有しておくことが重要です。
厚生労働省の対策マニュアルにて推奨されている、カスタマーハラスメントの事前準備・対策についてお伝えしていきます。 大まかな流れは以下の通りです。
① 会社の基本方針の明確化、従業員への周知・啓発
② 従業員のための相談対応体制の整備
③ 対応方法、手順の策定
④ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修
①、②は法改正によって義務付けられる内容となっています。
①の基本方針に含める内容の例としては、
- カスタマーハラスメントの内容
- カスタマーハラスメントは自社にとって重要な課題であること
- カスタマーハラスメントを放置しないこと
- カスタマーハラスメントから従業員を守ること
等が挙げられます。
会社のトップ自ら発信することで、会社が従業員を守ってくれる・カスハラを放置しないでいてくれるという従業員への安心感や、相談しやすい環境が作られることに繋がると考えられます。

②の相談対応体制では、相談対応者を決め、相談窓口を設置して従業員に広く周知することが求められます。形式上だけでなく実際に運用がスムーズにいくように、相談対応者への教育、相談を受けてからの対応・進め方のフローの作成等も行う必要があります。
③の対応方法・手順を策定する際には、実際に会社で起きた事例や、想定されることを具体的に洗い出し、それぞれへの対応例を準備しておくことが重要です。あらかじめ様々な想定をしておくことで、いざという時にスムーズに対応がしやすくなります。
また、対応手順を作成するうえで、実際にカスタマーハラスメント事案が発生した際の初期対応が重要となりますので、その点も詳しく盛り込んでおくと安心です。
初期対応で留意すべき具体的な事項は、以下の通りです。
- 限定的に謝罪する
- 状況を正確に把握する
- 現場監督者または相談窓口に情報共有する
1. 「限定的な謝罪」とは、顧客からの要求にすべて応えるような謝罪(たとえば、土下座を求められ土下座をする、自社の責任を問われて会社としての非を完全に認めて謝罪する、など)ではなく、対象を明確にしてそのことについてのみまずは謝罪するこということです。なぜなら、最初に顧客から要求を受けた時点では、正確な事実確認などができていないことがほとんどであるためです。
例)この度は、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。
2. 「状況の正確な把握」は、今後適切に対応を進める上で必要ですので、顧客の情報(氏名、連絡先等)や、顧客の主張(何を求めているのか)を聞き取るということです。
3. 上記で把握した内容を、速やかに現場監督者や相談窓口に共有します。最初に対応した従業員1人に抱え込ませるのではなく、会社として対応していくことがカスタマーハラスメント対応において重要です。
さらに、ここまでの流れで策定した対応方法・手順の通り対応できるように、④の教育・研修で、従業員等に浸透させることが重要です。

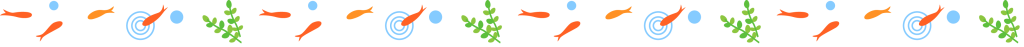
〇カスタマーハラスメント対策を怠ると…
会社としてカスタマーハラスメントに対して対策を講じず、放置してしまった場合には、改正後の法令を遵守していないというだけでなく、以下のような悪影響が考えられます。
- 従業員のパフォーマンス低下
- 従業員の身体・精神的な不調の発生
- 従業員の休職または退職
- 他の顧客の不満の発生
- 会社、店舗に対するブランドイメージの低下
特に、カスタマーハラスメントにおいて、会社は「従業員を守ること」が重要です。
法的な責任として安全配慮義務違反になる可能性があります。さらに、労災の判断基準の中にカスタマーハラスメントを受けることが追加されており、カスタマーハラスメントが原因で精神疾患等が発生した場合には労災事故として取り扱われることとなります。
こういったリスクを少しでも低減するためにも、カスハラ対策に取り組むことは重要です。
会社、従業員、そして他の顧客にとってもカスハラ対策を行うことはプラスに繋がりますので、ぜひ法改正を待たずに、早めに準備・対策を進めていただければ幸いです。