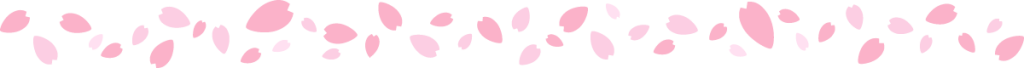「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」について
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されたことに伴い、雇用保険法が改正され、これまでの育児休業給付に加えて、令和7年4月1日から「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が創設されます。
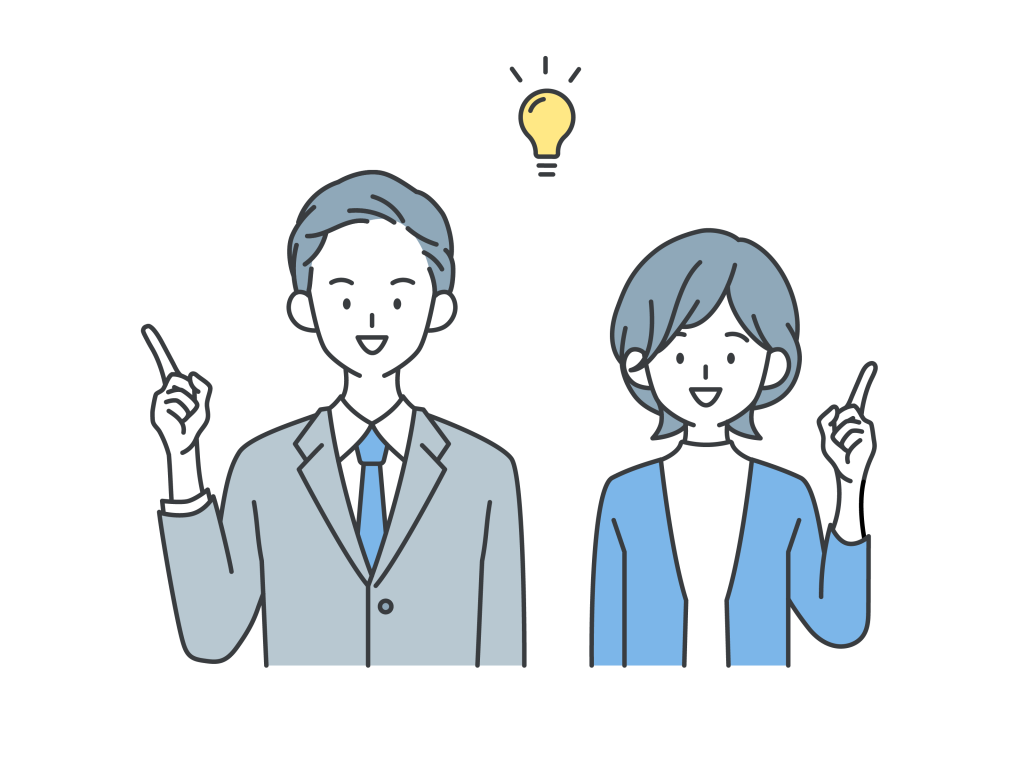
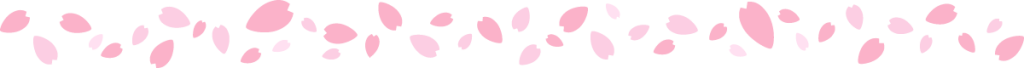
これまでの育児休業給付
育児休業給付金は、原則として、子が1歳になるまで支給されるもので、育児休業を開始してから180日目までは休業開始時賃金の67%相当が、181日目以降は休業開始時賃金の50%相当が支給されるものであり、父母ともに支給を受けることが可能です。女性の場合は、出産後56日間の産後休業の後に続く、育児休業から育児休業給付金の支給対象となり、男性の場合は、出産することがありませんので、休業をする場合は、育児休業からスタートし、その休業期間が育児休業給付金の支給対象となります。
男女問わずに育児休業を取得することは可能であるものの、男性の育児休業の取得率は、女性に比べると高くないことから、直近では、育児休業の分割取得及び出生時育児休業(産後パパ育休)に対する給付が創設されるなど、共働き・共育てに対する取組みは推進されています。

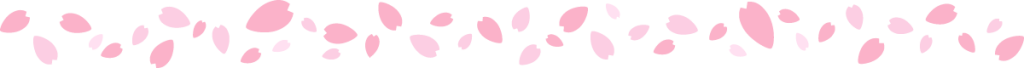
★出生後休業支援給付
背景
厚生労働省が実施した「令和5年度雇用均等基本調査」において、令和3年10月1日から令和4年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和5年10月1日までに育児休業を開始した者の割合は30.1%と発表されています。この数字は過去最高であるものの、政府は「こども未来戦略方針」において、「男性育休は当たり前」になる社会を目標としており、若者世代による共働き・共育ての推進と、男性の育児休業取得の更なる促進を目的に出生後休業支援給付が創設されました。
出生後休業支援給付とは
育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に上乗せして給付されるもので、子の出生直後の一定期間に、両親ともに育児休業を取得した場合に、出生後休業支援給付金が支給されます。

支給要件
以下①②をいずれも満たすことが必要です。
① 雇用保険の被保険者が、対象期間(※1)に同一の子について、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(※2)に該当していること。
※1 対象期間とは
- 父親または子が養子の場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間
- 母親かつ子が養子でない場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間
※2 配偶者の育児休業を要件としない場合
- 配偶者がいない
- 配偶者が行方不明(配偶者が雇用される労働者であり勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明となっている場合に限る。)
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 配偶者から暴力を受け、別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

支給額
出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後の一定期間内に夫婦が共に14日以上の育児休業をした場合に、休業開始時賃金日額の13%相当が最大28日間支給されます。
つまり、28日間の限定でありますが、休業開始時賃金の80%相当(育児休業給付金又は出生時育児休業給付金:67%+出生後休業支援給付金:13%)が支給されることとなります。
手取り10割相当
通常の給料の場合は、給料から社会保険料や税金が差し引かれ、額面上の給料に比べて、実際に受け取る給料は少なくなっています。個人差はありますが、一般的に額面上の金額から20%に当たる額(社会保険料及び税金)が控除され、手取り額は80%程度といわれています。
これに対し、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金については、社会保険料や、税金が掛かることもありません。
つまり、普段の給料では引かれているものが、引かれることなく受け取れるため、給付金の支給額が賃金の80%相当額といえど、休業前の手取り額と比較すると大きな差はないことから、実質手取り10割と表現されています。
支給申請手続
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。また、出生後休業支援給付金の支給申請のみを別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することになります。

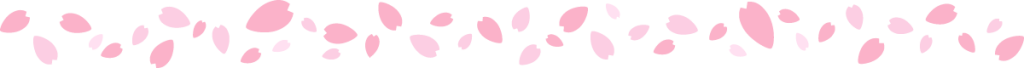
★育児時短就業給付
背景
厚生労働省が実施した「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査(令和4年度)」によると、育児のための短時間勤務制度については、「利用している」又は「以前は利用していた」の合計が、女性・正社員で51.2%であるのに対して、男性・正社員は7.6%という結果でありました。男性はもちろん、女性にとっても、この働き方が一般的に定着しているとは言い難く、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的として、育児時短就業給付が創設されました。
育児時短就業給付とは
これまで育児のための短時間勤務制度を利用した場合、通常の所定労働時間に比べて勤務時間が短縮されるため、給与もその分減額されるのが一般的でしたが、その減額された分の一部が給付金として支給される制度です。2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、当該時短勤務中に支払われた賃金に給付金が上乗せされます。
また、育児介護休業法により、3歳未満の子を養育する一定の労働者に対して、時短勤務の導入が義務付けられていますが、育児時短就業給付の対象となるのは、あくまで、2歳未満の子を養育することを目的とする時短勤務に限られています。つまり、2歳以降の子を養育することを目的として時短勤務をした場合は、育児時短就業給付の対象とはならず、子を養育することを目的とする全ての時短勤務が対象ではないということにご留意ください。

支給要件
以下①②をいずれも満たすことが必要です。
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること。
上記のほか、各月の支給要件は以下の通りです。
- 初日から末日まで続けて、被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額
育児時短就業給付金の額は、時短勤務中の給料の10%が上乗せされたものが支給されます。例えば、通常給与が30万円/月であった人が、時短勤務をしたことにより、25万円/月となった場合、この25万円に対する10%(2万5千円)の給付金が支給され、当該月については、給与分の25万円と給付金の2万5千円とを合わせて27万5千円が支給されることとなります。
ただし、時短勤務に係る賃金と育児時短就業給付金との合計が、時短勤務開始前の賃金額を超えないように支給率は調整されますので、必ずしも時短勤務における給料の10%が支給されるわけではありません。
支給対象期間
育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。育児休業から4月21日に復帰し、同日から時短就業を開始し、翌年の3月20日まで時短就業を行った場合は、育児時短就業を開始した日の属する月である4月から育児時短就業を終了した日の属する月である翌年の3月までの各歴月が支給対象月となります。
ただし、この期間内に次のいずれかに該当する日がある場合については、その日の属する月までが支給対象となる月の最終月となります。
- 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
- 産前産後休業、育児休業又は介護休業を開始した日の前日
- 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前月末日
- 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

経過措置
令和7年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、令和7年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記の要件や育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、令和7年4月1日以降の各月を支給対象月として支給します。
また、復職してから時短勤務までの間が14日以内であれば、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したものとして取り扱われることから、以下のように整理されます。
例1
令和7年3月17日以前に、育児休業から復帰して引き続き育児時短勤務を開始した場合
⇒ 令和7年4月1日から遡って、被保険者期間・賃金日額を確認・算定する。
例2
令和7年3月18日以降に、育児休業から復帰して引き続き育児時短勤務を開始した場合
⇒ 被保険者期間の確認は要さず、育児休業給付に係る休業開始時賃金日額を賃金日額とする。
例3
令和7年3月31日以前に、育児時短勤務を開始した場合(育児休業から連続しないとき)
⇒ 令和7年4月1日から遡って、被保険者期間・賃金日額を確認・算定する。